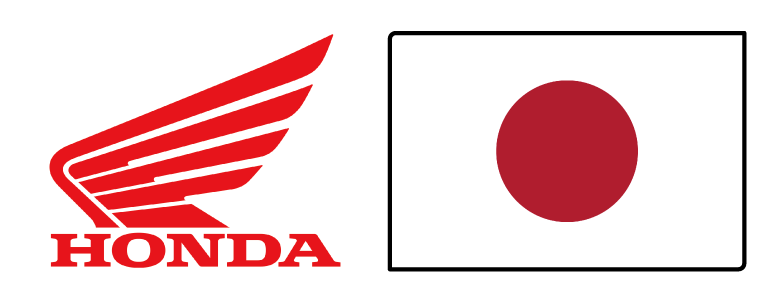 CR93 ベンリィレーシング
CR93 ベンリィレーシング
プライベーターの至宝:ホンダCR93ベンリィレーシング
野心が生んだ黎明期:ホンダ・プロダクションレース時代の幕開け
1962年という転換点
1962年は、ホンダにとって、そして日本のモータースポーツ史にとって画期的な年となった。この年、世界水準の国際レーシングコースである鈴鹿サーキットが完成し、時を同じくして日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ)が発足した。そして同年9月にCR93を発表する。新設されたサーキットを舞台に、新たな統括組織のもとで戦うプライベートレーサーたちの手に、世界最高水準の「武器」を供給することこそが、CR93に与えられた使命だった。
グランプリの勝利から、市販レーサーへ
CR93の登場以前、ホンダはすでに世界のレースシーンでその技術力を証明していた。1959年のマン島TTレースへの初挑戦からわずか2年後の1961年には、ロードレース世界選手権の125ccおよび250ccクラスで圧倒的な強さを見せ、メーカーチャンピオンの栄冠に輝いていた。この成功の核となったのが、"RC"の名を冠するワークスレーサー群であり、その心臓部には当時世界で最も先進的であった小排気量4ストロークエンジンが搭載されていた。CR93の開発とは、この門外不出であったはずのチャンピオンマシンの技術を、一般のレーサーが購入可能な「市販車」へと転用するという、革命的な決断そのものであった。
ホンダの意思表明
50ccのCR110と同時に発表されたCR93は、ホンダ史上初の市販ロードレーサーであった。これは、ホンダが自社のワークスチームの勝利だけに満足しているのではないという、世界に対する力強い意思表明に他ならなかった。優れたマシンをプライベーターの手に広く行き渡らせることで、モータースポーツの裾野を広げ、あらゆるレベルのレースにおいてホンダの技術的優位性を確立する。CR93の存在は、ホンダが単なるメーカーから、モータースポーツという巨大な生態系を創造し、主導する存在へと飛躍しようとしていることを明確に示していた。
この一連の動きは、ホンダによるモータースポーツ・エコシステムの垂直統合戦略と見ることができる。まず、世界に通用する舞台として鈴鹿サーキットを建設し、競技のルールと格式を整備する統括組織としてMFJの発足を後押しした。そして、その舞台で戦う主役であるレーサーたちに、最高の機材としてCR93とCR110を提供する。サーキット、運営組織、そしてマシンというレースに不可欠な三要素を同時に供給することで、ホンダは日本のロードレース新時代の主導権を完全に掌握した。それは、自社の技術を普及させ、才能あるライダーを発掘し、ブランドの威信を不動のものとするための、長期的かつ巧みな戦略だったのである。
チャンピオンの心臓:CR93レーシング・テクノロジーの深淵
CR93レーシングを理解する上で最も重要なのは、このマシンが純粋な競技用車両として設計されたという事実である。その技術的特長のすべてが、サーキットでの勝利という唯一の目的のために注ぎ込まれている。特に、公道走行可能なストリートモデルと比較すると、その差異は歴然であり、CR93レーシングがロードレース世界選手権を制したワークスマシンRCシリーズの正統な後継者であることを雄弁に物語っている。
ワークス直系のエンジン「CR93E」
CR93レーシングの心臓部であるCR93E型エンジンは、まさしく「公道を走ることを許されなかったワークスエンジン」そのものであった。空冷4ストローク並列2気筒、排気量124.8ccという基本構成はストリートモデルと共通だが、レーシングキットを取り付けた際の最高出力は、16.5 PS / 11,500 rpmを凌駕する21.5 PS / 13,500 rpmを発生させたとも伝えられている。125ccクラスにおいて、この30%以上もの出力差は、勝敗を決定づける絶対的なアドバンテージであった。この驚異的な高回転・高出力を実現したのが、ワークスレーサーRC143やRC145から直接受け継いだ、1気筒あたり4バルブを持つDOHC(ダブル・オーバーヘッド・カムシャフト)という弁機構である。1960年代初頭の市販125ccマシンとしては、まさに異次元のテクノロジーであった。また、ボア(内径)とストローク(行程)を共に43.0 mmとするスクエア設計は、高回転化を追求したレーシングエンジンならではの選択であった 。
精密さの象徴「カムギアトレーン」
この高性能エンジンを技術的に定義づけるのが、ホンダの代詞とも言える「カムギアトレーン」である。一般的なエンジンがカムシャフトの駆動にチェーンを用いるのに対し、CR93Eはクランクシャフトからカムシャフトまで、複数の歯車(ギア)を介して回転を伝達する方式を採用していた。
グランプリマシンから直接フィードバックされたこの機構は、超高回転域においても極めて正確なバルブタイミングを維持することを可能にする。チェーン駆動で起こりうる、チェーンの伸びや振動による微妙なタイミングのズレ(バルブサージングやバルブフロート)を根本的に排除し、13,500 rpmという途方もない回転数までエンジンを安全に回し切るための、まさに生命線であった。クランクケースからシリンダーヘッドへと伸びるギアの駆動音は、CR93が特別なマシンであることを示す、性能の証でもあった。
二つの戦線での征服:国内外におけるCR93の勝利
CR93ベンリーレーシングは、その登場と同時に、国内外のサーキットで圧倒的な戦闘能力を発揮し、その名をモータースポーツ史に刻み込んだ。特に、世界で最も権威ある公道レース「マン島TT」と、黎明期の国内レースシーンを象徴する「全日本モーターサイクルクラブマンレース」での活躍は、このマシンが持つ世界水準の性能を証明するものであった。
マン島TTレース:世界への性能証明
1962年のマン島TTレース、ライトウェイト125ccクラスにおいて、ホンダのマシンは1位から5位までを独占するという、歴史的な完全制覇を成し遂げた。優勝したルイジ・タベリをはじめ、トミー・ロブ、トム・フィリスらが駆ったのはホンダのワークスレーサーRC145であったが、この勝利はCR93にとって極めて重要な意味を持っていた。なぜなら、この世界最高峰のレースで圧勝したワークスマシンの心臓部、すなわちカムギアトレーン駆動の4バルブDOHCエンジンという最先端技術が、ほぼそのままの形で市販レーサーCR93に搭載されていたからである。
プライベーターは、CR93を購入することで、マン島を制したのと同じ血統を持つテクノロジーを手にすることができた。一部の記録では、CR93そのものがマン島TTで3位に入賞したとも伝えられており、これは市販レーサーがワークスマシンと互角に渡り合ったことを示す驚異的な出来事である。この活躍により、CR93は単なる国産レーサーではなく、世界の頂点で戦える性能を持つ「グローバル・スタンダード」としての評価を確立した。
雁ノ巣クラブマンレース:国内戦線の制圧
国際舞台での名声と並行して、CR93は日本のレースシーンにおいてもその支配力を示した。1962年7月、福岡県の雁ノ巣(がんのす)飛行場に設けられた特設コースで開催されたイベントは、当時の国内レースシーンを象徴する重要な一戦であった。この大会では「第5回全日本モーターサイクルクラブマンレース」と「日本選手権レース」が併開催され、CR93はその両方で圧倒的な強さを見せつけた。
まず、「クラブマンレース」の125ccクラス決勝において、テクニカルスポーツチームからエントリーしたCR93がワンツーフィニッシュを飾る。優勝したのは渥美勝利(あつみ かつとし)選手、そして2位にはチームメイトの大月信和(おおつき のぶかず)選手が続いた。さらに、同日開催された格式の高い「日本選手権レース」125ccクラスでは、この二人の順位が入れ替わり、大月信和選手が見事優勝、渥美勝利選手が2位に入るという、CR93による完全制圧を成し遂げた。
この雁ノ巣でのダブル勝利、特に同一チームによる表彰台独占は、日本のプライベートレーサーたちにとって衝撃的であった。マン島という遠い異国の地での勝利だけでなく、身近な国内のサーキットで、自分たちと同じ日本のライダーがCR93を駆って勝利したという事実は、このマシンの実用性と戦闘能力を何よりも雄弁に物語っていた。
ホンダが展開した戦略は、二方面作戦として見事に結実した。マン島TTでの活躍は、CR93に国際的な権威と技術的優位性の「お墨付き」を与えた。一方で、雁ノ巣での勝利は、国内の顧客に対する最も効果的な「実演販売」となった。世界レベルの性能を持つマシンが、国内のレースで実際に勝利を収める。この二つの勝利が一体となることで、「CR93こそが勝利への最短距離である」という、揺るぎないブランドイメージが構築されたのである。
希少性という名の伝説:CR93が幻となるまで
ホンダCR93ベンリーレーシングは、その卓越した性能だけでなく、現存する個体数が極めて少ないことでも知られている。その希少性は、単に生産台数が少なかったというだけではなく、このマシンが背負った宿命と、当時のレース規則という特殊な事情が複雑に絡み合った結果生み出されたものである。CR93は、その生まれながらにして、伝説となるべく運命づけられていた。
極端に少ない生産台数
CR93の総生産台数は、レーシングモデルとストリートモデルを合わせても、わずか200台から250台余りであったと推定されている。この数字自体が、量産車とは一線を画す希少性を示している。さらに、これらのマシンの多くは、その生来の目的通り、国内外のレースシーンへと投入された。
競技車両の宿命として、激しいレースの中で転倒による損傷は日常茶飯事であった。また、性能を維持・向上させるために改造が加えられたり、他のマシンのための部品取りに使われたりすることも少なくなかった。結果として、製造されたCR93の多くがレースキャリアの中で失われ、オリジナルの状態を保ったまま現存する個体は、ごく一握りとなってしまった。特に、ヨーロッパへの輸出が多かったことも、日本国内での残存数をさらに少なくする要因となった。
ストリートモデル誕生の真相:1962年のMCFAJホモロゲーション規則
CR93の希少性を語る上で欠かせないのが、なぜ公道走行可能なストリートモデルが存在するのか、という点である。その答えは、1962年シーズンに限定して施行された、全日本モーターサイクルクラブ連盟(MCFAJ)の特殊な車両規則にある。
この年のノービスクラス(入門クラス)のレースでは、参加する車両が運輸省(現在の国土交通省)による型式認定を受けていること、すなわち公道走行可能な市販車であることが義務付けられた。ホンダは、自社の顧客であるプライベートレーサーたちがこのクラスに参加できるよう、純粋なレーシングマシンであったCR93にヘッドライトやテールランプなどの保安部品を装着し、公道走行に必要な認可を取得したモデルを生産する必要に迫られた。これが、CR93ストリートモデルが誕生した唯一の理由である。それは、市場のニーズに応えるためではなく、レースの規則をクリアするためだけに作られた「ホモロゲーション・スペシャル」であった。
この事実は、CR93というマシンの本質を理解する上で極めて重要である。ホンダが本来作りたかったもの、そしてプライベーターたちが真に求めていたものは、一切の妥協を排した純粋なレーシングモデルであった。ストリートモデルの存在は、その目的を達成するための、いわば副産物であった。この背景を鑑みると、CR93レーシングこそが、開発者たちの意図を最も純粋な形で体現した「真のCR93」であると言える。
CR93レーシングの希少性は、その絶対的な生産数の少なさだけでなく、その存在意義そのものに根差している。ストリートモデルがレース規則という外的要因によって生まれた「必要悪」であったのに対し、レーシングモデルは勝利という唯一無二の目的のために生まれた「純粋な存在」であった。
革命の反響:CR93が遺した不滅の技術的遺産
ホンダCR93ベンリーレーシングがレースシーンから姿を消した後も、その技術的な魂は消えることなく、後継となる数々の名車へと受け継がれていった。特に、超高回転を精密に制御するカムギアトレーン駆動のDOHCエンジンは、ホンダの高性能4ストロークエンジンの象徴となり、その後のブランドアイデンティティを決定づける重要な技術的血脈となった。CR93は、1960年代の成功作ではなく、ホンダの現代に至る高性能スポーツバイクの系譜を築き上げた、偉大なる始祖なのである。
カムギアトレーンのDNA
CR93は、ホンダがグランプリで培ったカムギアトレーンという技術を、初めて一般のライダーに解放した記念碑的なモデルであった。精密な歯車の組み合わせが奏でる独特の駆動音は、高性能の証としてライダーの心を掴み、ホンダを象徴するメカニズムとして認知されていった。この技術的DNAは、時代を超えてホンダの高性能モデルに脈々と受け継がれていく。
CB-Fシリーズ(1970年代後半~80年代初頭): 70年代のレースシーンを席巻した耐久レーサーRCBの技術をフィードバックして生まれたCB900FやCB750Fは、DOHCエンジンを採用し、大排気量スポーツバイクの世界にホンダの復権を印象付けた。その設計思想の根底には、CR93で確立された高性能4ストロークエンジンへの信頼があった。
CBX1000(1979年): ホンダの技術力の結晶とも言える空冷6気筒DOHCエンジンを搭載したCBXは、60年代の多気筒ワークスレーサーの思想を公道で再現したモデルであり、その精密なバルブ駆動機構はCR93の系譜に連なるものであった。
CBR250RR/400RR(1980年代後半〜90年代): 熾烈な性能競争が繰り広げられた日本のレプリカブームにおいて、ホンダは再びカムギアトレーンをサーキットから呼び戻す。CBR250RRやCBR400RRに搭載された超高回転型4気筒エンジンは、カムギアトレーンを「レーシングテクノロジーの証」として明確に打ち出し、19,000 rpmという驚異的なレッドゾーンを実現した。ライダーたちは、その甲高いエキゾーストノートと共に響くギアの駆動音に、ホンダのレースの歴史と魂を感じ取ったのである。
高回転・高性能哲学の確立
より広い視点で見れば、CR93は「4ストロークエンジンは、優れた技術と高回転化によって、シンプルでパワフルな2ストロークエンジンに対抗し、凌駕することができる」というホンダの基本哲学を、市販車の世界で初めて証明したマシンであった。1960年代から70年代にかけて、ライバルであるヤマハやスズキが2ストロークエンジンの開発に注力する中、ホンダは一貫して複雑で精密な4ストローク高性能エンジンの可能性を追求し続けた。CR93は、その哲学が一般のライダーにもたらした最初の、そして最も鮮烈な果実だったのである。
CR93は、ホンダの高性能スポーツバイクという一大ジャンルの源流に位置する、記念碑的な存在である。それまでワークスチームという聖域に秘匿されていたグランプリのDNAが、初めてプライベーターの手に渡った瞬間、それがCR93の誕生であった。1990年代の若者がCBR250RRのカムギアトレーンが奏でる音に胸を躍らせた時、彼らが体験していたのは、その30年近く前にCR93が切り拓いた技術と哲学の、正統な進化の形なのである。CR93はホンダのファミリーツリーにおける一本の枝ではなく、高性能スポーツバイク部門全体を支える、力強い根そのものであると言えよう。
The Immortal Legacy of the Honda CR93 Benly Racing
In 1962, Honda released its first-ever production road racer, the CR93 Benly Racing. Timed with the completion of the Suzuka Circuit and the establishment of the Motorcycle Federation of Japan (MFJ), this strategic machine heralded a new era for motorsports in Japan. Honda's goal was to provide privateer racers with the cutting-edge technology it had cultivated in world championships, thereby expanding the base of the sport.
At the heart of the CR93 was a DOHC 4-valve engine derived directly from the world-championship-winning RC series factory racers. Its core technology was the "cam gear train," which enabled precise valve timing even at ultra-high RPMs. It produced a maximum output of 21.5 PS at 13,500 rpm, boasting overwhelming performance for a 125cc machine of its time. While a street-legal version existed, it was a homologation special built solely to meet race eligibility requirements; the CR93 was, in essence, a purebred racing machine.
Its performance was proven in races both in Japan and abroad. At the 1962 Isle of Man TT, the factory machines that formed the basis of the CR93 dominated the top positions, demonstrating its world-class capabilities. In Japan, it achieved a resounding victory at the Gannosu Clubman Race in Fukuoka, stunning local racers.
With a total production of only around 250 units, the CR93 is exceedingly rare. However, the philosophy it established--of high-revving, high-performance 4-stroke engines with cam gear trains--became an immortal legacy inherited by later Honda high-performance sport bikes like the CB-F and CBR series. The CR93 is not merely a classic motorcycle; it is the great ancestor that symbolizes Honda's racing DNA.
本田 CR93 Benly Racing 的不朽遺產
1962年,本田(Honda)發表了史上首款市售公路賽車「CR93 Benly Racing」。這款戰略性車型與鈴鹿賽道的落成及日本摩托車運動協會(MFJ)的成立同步,為日本賽車運動開拓了新時代。其目標是將本田在世界錦標賽中累積的頂尖技術提供給私人車手,藉此擴大賽車運動的基礎。
CR93 的心臟是源自稱霸世界錦標賽的工廠賽車 RC 系列的 DOHC 4汽門引擎。其核心技術為「凸輪齒輪驅動系統 (cam gear train)」,即使在超高轉速下也能實現精準的汽門正時。其最大馬力達到 21.5 PS / 13,500 rpm,在當時的 125cc 級別中擁有壓倒性的性能。雖然也存在街道版,但那只是為了取得參賽資格的認證車型 (homologation model),CR93 的本質是一部純粹的競賽機器。
其卓越性能在國內外賽事中得到證明。在1962年的曼島TT大賽中,作為CR93基礎的工廠賽車獨佔了頒獎台,印證了其世界級的實力。在日本國內,它也在福岡縣的雁之巢俱樂部人賽事中大獲全勝,震撼了日本的賽車手們。
總產量僅約250輛,使CR93極為稀有。然而,它所確立的凸輪齒輪驅動與高轉速四行程引擎的理念,成為了不朽的遺產,被後來的 CB-F 和 CBR 系列等本田高性能運動車款所繼承。CR93 不僅是一輛經典名車,更是象徵本田賽車DNA的偉大始祖。