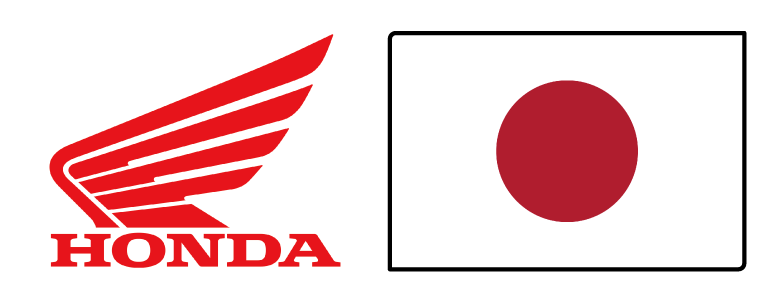 ドリーム CB750 four K0
ドリーム CB750 four K0
ドリーム・マシン:ホンダ CB750 FOUR K0 がいかにして一つの時代を定義したか
I. 再興する国家が生んだ巨人:1969年の世界
ホンダCB750 FOUR。それは、戦後の日本の熱い思いと、1960年代後半の文化的な大きなうねりが一つになった、まさにその時代を象徴するバイクだった。このマシンを理解するには、それが生まれた土壌、すなわち日本の社会経済的背景を深く掘り下げる必要がある。
昭和元禄の輝きと熱狂
1960年代後半、日本は「昭和元禄」とも称される未曾有の高度経済成長の絶頂期にあった。実質経済成長率は年平均12.4%という驚異的な数値を記録し、国家全体が自信と活力に満ち溢れていた。この経済的繁栄は、石炭から石油へのエネルギー転換、重化学工業化、そして官民一体となった大規模な設備投資によって支えられていた。1964年の東京オリンピック、東海道新幹線、そして1970年の大阪万国博覧会といった国家的な祭典は、日本が国際社会の表舞台へ完全に復帰したことを世界に示す象徴的な出来事だった。CB750は、まさにこうした技術の勝利を象徴する存在だったと言えるだろう。
この経済的な豊かさは、新たな文化のダイナミズムを生み出した。ビートルズに代表される世界的な潮流に影響された若者たちは、旧来の価値観からの脱却と、新しい形の自由や自己表現を渇望していた。オートバイは、個人の自由を象徴する乗り物として、この世代の欲求を叶える強力な器となった。しかし、この急成長は光ばかりではなかった。臨海工業地帯を中心に深刻な公害問題が発生し、社会に暗い影を落としていた。物質的な豊かさの裏には、「豊かさの病理」とも言うべき社会・環境問題が潜んでおり、この時代の複雑さを物語っている。CB750が後に社会的な混乱と結びつけられることになるのも、この時代の光と影の側面を映し出していると言えるだろう。
日本のオートバイは1950年代から60年代初頭にかけて、まだまだ欧米製品の模倣から脱却できずにいた。しかし、60年代後半には、日本は世界有数の工業大国へと変貌を遂げ、高度な研究開発と高品質な製造能力を獲得していた。すでにロードレース世界選手権でその技術力を証明していたホンダは、その能力を市販車へと注ぎ込んだ。その結果生まれたCB750は、単なる模倣品ではなく、業界全体を根底から覆す革命的な跳躍であった。並列4気筒エンジンやディスクブレーキといった先進技術は、まさにユーザーの言葉通り「これまでの品質と性能を否定」するものであり、未来を定義する新たな日本の自信を世界に提示したのである。
II. 伝説の序章:1968年東京モーターショー
CB750が「生まれる前から伝説」となった背景には、その劇的なデビューがあった。1968年10月の東京モーターショーで、ホンダは「ドリームCB750 FOUR」のプロトタイプを世界に公開した。その反響は単なる称賛にとどまらず、世界中のライダーと専門家を震撼させるほどの衝撃であった。
想像を超えたマシン
そのスペックは、それまでの量産二輪車の常識を完全に覆すものだった。
ロードレース世界選手権を戦ったレーシングマシンを彷彿とさせる、750ccの並列4気筒エンジン。
量産二輪車としては世界初となる、油圧式フロントディスクブレーキの採用。
エンジンから伸びる4本のきらびやかなエグゾーストパイプが織りなす、威風堂々たるスタイリング。
これらの要素が組み合わさった圧倒的な存在感の前に、CB750は発売される前からプレスや大衆によって「キング・オブ・ロードマシン」の称号を与えられた。そのあまりのビッグサイズに、創業者である本田宗一郎ですら「こんなにデカイの、誰が乗るんだ?」と驚きの声を上げたという逸話は、このマシンがいかに規格外であったかを物語っている。
この衝撃的な発表は、単なる偶然の産物ではなく、ホンダの巧みな産業・マーケティング戦略の賜物であった。当時、ライバルであるカワサキが同様に大排気量4ストローク車の開発を進めていることをホンダは察知していた。1968年の時点で、世界初の機能を多数搭載した完成度の高いコンセプトモデルを提示することで、ホンダは技術革新の主導権を完全に掌握した。これによりカワサキは計画の見直しを余儀なくされ、単にCB750に追随するのではなく、それを凌駕するマシンの開発へと舵を切らざるを得なくなった。この戦略的な一手は、カワサキの市場投入を遅らせ、ホンダに先行者利益をもたらしたのである。
III. CB750 FOUR K0の技術
当博物館に展示されているのは、CB750 FOURの中でも最初期に生産された「K0」と呼ばれるモデルである。このモデルの技術的な詳細を紐解くことで、なぜこの一台が革命的であったのか、そしてなぜK0、特に初期の「砂型」モデルが特別視されるのかが明らかになる。
野獣の心臓:SOHC並列4気筒エンジン
CB750の心臓部である736cc空冷並列4気筒エンジンは、最高出力67馬力を8,000rpmで発生させた。これは、ホンダがロードレース世界選手権で培った最先端技術を市販車にフィードバックしたものであり、量産二輪車としては世界初の並列4気筒エンジンであった。それまでのモーターサイクルでは考えられなかったほどの滑らかさと、淀みないパワーデリバリーを実現し、ライダーに全く新しい走行体験を提供した。
砂型の魂:最初期K0の希少性
K0の中でも、ごく初期に生産された約7,500台は、「砂型鋳造(すながたちゅうぞう)」と呼ばれる特殊な製法で造られたクランクケースを持つ。これは、部品一つひとつに対して砂で鋳型を作る、手間のかかる少量生産向けの製法である。このため、エンジンケースの表面は独特のざらついた肌触りを持つのが特徴だ。ホンダは当初、年間販売台数を1,500台程度と予測しており、この製法で十分対応可能だと考えていた。しかし、予測を遥かに超える注文が殺到したため、大量生産に適した高圧鋳造(金型)へと製法を切り替えざるを得なくなった。金型で製造されたケースは、砂型に比べて滑らかな表面を持つ。このため、極めて限られた期間しか生産されなかった「砂型」エンジンを搭載したK0は、その希少性と独特の製造背景から、コレクターの間で極めて高い価値を持つに至っている。
K0をK0たらしめる特徴
展示されているK0モデルには、後のK1モデルとは一線を画す、数多くの初期型ならではの特徴が見られる。
ブレーキ革命:世界で初めて量産二輪車に採用された油圧式フロントディスクブレーキは、200km/hに達する最高速度に見合う、信頼性の高い制動力を提供し、安全性の概念を大きく前進させた。
車体とデザイン:ホンダ初となるダブルクレードルフレームを採用し、高速走行時の安定性を確保。そして、マシンの象徴とも言える左右2本ずつの4本出しマフラーは、その後の日本製大型バイクのデザインに絶大な影響を与えた。
K0固有のディテール:このモデルには、より量産効率が追求されたK1とは異なる、初期生産ならではの仕様が残されている。スロットルケーブルは引き側のみの1本引き、サイドカバーは角張った張り出しの強い形状、スピードメーターは240km/hまで目盛りが刻まれ、タコメーターのレッドゾーンは8,500rpmから始まっている。また、シート後端が跳ね上がったデザインもK0の大きな特徴である。
これらのK0とK1の違いは、いわゆるマイナーチェンジという表現だけでは説明が足りない。それは、ホンダが予期せぬ世界的需要という嬉しい悲鳴に応えるため、いかにして手作りに近い少量生産から、世界規模の大量生産へと移行していったかの苦闘の記録そのものである。砂型エンジンの荒々しい鋳肌や、1本引きのスロットルといった「未完成」とも言える部分は、このマシンが量産ラインのために完全に合理化される前の、より純粋な初期衝動を宿している証なのである。
表1: ホンダ CB750 FOUR K0 (1969) 主要諸元
| 項目 | スペック |
|---|---|
| エンジン形式 | 空冷4ストローク並列4気筒SOHC2バルブ |
| 総排気量 | 736cc |
| 内径×行程 | 61.0mm × 63.0mm |
| 最高出力 | 67ps / 8,000rpm |
| 最大トルク | 6.1kgf・m / 7,000rpm |
| 変速機 | 5速リターン |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| ブレーキ | 前:油圧式ディスク / 後:ドラム |
| タイヤ | 前:3.25-19 / 後:4.00-18 |
| 全長×全幅×全高 | 2,160mm × 885mm × 1,120mm |
| 燃料タンク容量 | 19 L |
| 最高速度 | 200 km/h |
表2: K0からK1への主な生産変更点
| 特徴 | CB750 FOUR K0 (1969-1970) | CB750 FOUR K1 (1970-1971) |
|---|---|---|
| エンジンケース鋳造 | 砂型(初期)/ 金型(後期) | 金型 |
| スロットルケーブル | 1本引き | 2本引き(強制開閉式) |
| サイドカバー形状 | 角張った張り出し形状 | 足つき性向上のため、よりフラットな形状 |
| エアクリーナーケース | 外装と同色 | ブラック |
| スピードメーター | 240km/hスケール | 220km/hスケール |
| タコメーターレッドゾーン | 8,500rpmから | 8,000rpmから |
| シート形状 | 後端が跳ね上がった形状 | フラットな形状 |
IV. ホンダ・ショックウェーブ:世界のモーターサイクル市場の再定義
CB750の登場は、業界に巨大な衝撃波を送り、世界の主要メーカー全てに対応を迫り、「スーパーバイク」という新たなカテゴリーを創出した。
明石からのライバル:カワサキZ1の誕生
CB750登場以前、カワサキはすでに「N600」というコードネームで、独自の750cc DOHC並列4気筒エンジンの開発を進めていた。しかし、1968年のホンダによるCB750の発表は、カワサキにとってまさに「寝耳に水」の出来事であった。彼らは、この時点で単にCB750と同等のマシンを市場に投入しても、後追い製品の烙印を押されるだけだと悟った。そこでカワサキは、「ニューヨーク・ステーキ」という開発コードのもと、750ccの計画を一度白紙に戻し、あらゆる性能指標でホンダを明確に凌駕する、全く新しいマシンの開発へと踏み切るという大胆な決断を下す。その結果生まれたのが、排気量を903ccにまで拡大し、よりパワフルで、より高速なカワサキZ1であった。CB750はZ1にインスピレーションを与えただけでなく、それをより過激で強力なモーターサイクルへと昇華させる「強制力」として働いたのである。
競合の応酬:スズキとヤマハの回答
CB750が確立した4ストローク・4気筒という牙城に対し、スズキは正面からの対決を避けた。代わりに、自社が得意とする2ストローク技術を極限まで高める道を選ぶ。こうして生まれたのが、750cc・2ストローク・3気筒エンジンに、当時としては極めて画期的な水冷システムを組み合わせたGT750である。その重厚な乗り味から「ウォーターバッファロー」の異名を取り、CBのスポーツ性とは対照的な、パワフルで滑らかなグランドツアラーとして独自の地位を築いた。
一方、高性能な2気筒エンジンで名を馳せていたヤマハも750ccクラスに参入する。ヤマハが投入したTX750は、750ccのSOHC並列2気筒エンジンを搭載していた。ホンダの4気筒が持つ滑らかさに対抗するため、「オムニフェイズ・バランサー」という複雑な振動低減機構を採用したが、このモデルは信頼性の問題に悩まされ、ホンダやカワサキの多気筒モデルが巻き起こした熱狂の中に埋もれてしまった。
CB750が持つ750ccという排気量はあまりに象徴的であったため、日本の言葉に新たな単語を生み出した。それが「ナナハン」である。この言葉は、単なる排気量を指す数字を超え、ライダーの憧れの的となる最高峰クラスのオートバイそのものを意味するようになった。
このように、CB750は単に新しい製品を生み出しただけではなかった。それは、高性能モーターサイクル市場の構造と日本のバイク乗りの憧憬を根本から作り変えたのである。CB750は市場の中心となり、他のすべてのメーカーをその周回軌道へと引き込んだ。カワサキのように直接対決を挑むか、スズキのように技術的な差別化を図るか、あるいはヤマハのように旧来のパラダイムに固執して苦戦するか。1970年代に繰り広げられた「ナナハン戦争」として知られる熾烈な開発競争は、すべてCB750の登場が火をつけた結果だった。
表3: ナナハン戦争:競合モデル概観(1973年頃)
| メーカー | モデル名 | 発売年 | エンジン形式 | 総排気量 | 最高出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホンダ | ドリームCB750 FOUR | 1969 | 空冷4スト並列4気筒SOHC | 736cc | 67ps |
| カワサキ | 900 Super4 (Z1) | 1972 | 空冷4スト並列4気筒DOHC | 903cc | 82ps |
| カワサキ | 750RS (Z2) | 1973 | 空冷4スト並列4気筒DOHC | 746cc | 69ps |
| スズキ | GT750 | 1971 | 水冷2スト並列3気筒 | 738cc | 67ps |
| ヤマハ | TX750 | 1972 | 空冷4スト並列2気筒SOHC | 743cc | 63ps |
V. 炎の試練:1970年デイトナ200マイルレースの勝利
CB750の伝説を不動のものとしたのが、レースでの劇的な勝利である。その舞台は、世界で最も過酷で権威あるレースの一つ、デイトナ200マイルレースであった。
巨人たちの激突
1970年のデイトナは、ホンダの新型CB750、トライアンフ/BSAの新型3気筒マシン、そしてハーレーダビッドソンの新型XR750TTが覇を競う、まさに巨人たちの戦場となるはずだった。ホンダは、このレースのために4台のファクトリーマシンを投入した。しかし、練習走行の段階で、市販車では問題にならなかった重大な欠陥が露呈する。レーシングスピードで酷使されたエンジンのカムチェーンテンショナーが崩壊し、その破片がオイルに混入するという、エンジンブローに直結しかねない致命的なトラブルであった。
アメリカの知恵とベテランの腕
この問題をいち早く見抜いたのが、ボブ・ハンセン率いるアメリカ・ホンダのチームだった。メカニックのボブ・ジェイムソンは、市販車の整備経験から、オイルに混じる黒い異物が何を意味するかを即座に理解した。彼らは、自チームのライダーであった36歳のベテラン、ディック・マンのマシンのエンジンを夜通しで分解・修理し、テンショナーを交換した。しかし、他の3台のホンダマシンを担当していたチームは、この警告を重要視しなかったと伝えられている。
決勝レースは、まさにサバイバル戦となった。ジェイムソンの懸念通り、ディック・マン以外の3台のホンダファクトリーマシンは、次々とエンジントラブルでリタイア。伝説的ライダー、マイク・ヘイルウッドが駆るBSAを含む、強力なライバルたちもまた、メカニカルトラブルで次々と姿を消していった。
知性がもたらした勝利
その中で、ディック・マンはマシンを労わる知的な走りに徹した。彼はエンジンの限界を熟知し、回転数を抑えることで、壊れやすいエンジンをゴールまで導いたのである。レース終盤、猛追するジーン・ロメロをわずか数秒差で振り切り、チェッカーフラッグを受けた。ゴールした彼のマシンは3気筒しか作動しておらず、エンジンにはほとんどオイルが残っていなかったという。
この勝利は、ディック・マンにとって15回目の挑戦で掴んだ初のデイトナ制覇であり、同時に、ホンダにとってAMAナショナルレースにおける歴史的な初勝利でもあった。この劇的な勝利は、CB750の高性能と、そして皮肉にもその耐久性を、世界で最も過酷な舞台で証明し、その名を伝説として刻み付けたのである。この勝利の物語は、単なるマシンの優位性によるものではない。それは、アメリカ人チームの実践的な知恵が日本の最新技術を救い、ベテランライダーの経験と判断力がライバルたちの若さとスピードを上回った、人間ドラマの勝利であった。
VI. 偉大さの影:CB750が日本社会に残した功罪
CB750は、母国である日本において、技術的な栄光とは裏腹の、複雑で論争に満ちた社会的遺産を残した。その圧倒的な成功こそが、日本の社会に深刻な課題を突きつける原因となったのである。
暴走族の象徴として
1970年代に入ると、CB750の持つ圧倒的なパワー、威厳、そして「ナナハン」という特別な響きは、社会への反抗心を示す若者集団、すなわち暴走族にとって、究極のステータスシンボルとなった。彼らの危険な集団走行や抗争事件は深刻な社会問題となり、CB750はその中心的なアイコンとして認識されるようになった。
規制の引き金:「750cc自主規制」
高性能バイクの急増と、それに伴う交通事故の増加や暴走族問題の深刻化を受け、行政の指導のもと、日本自動車工業会は国内で販売する二輪車の排気量上限を750ccとする「自主規制」を導入した。この規制は、CB750の登場がきっかけとなったと言っても過言ではない。これにより、カワサキは輸出用に903ccのZ1を製造する一方で、日本国内市場向けには、わざわざ750ccにスケールダウンした750RS(Z2)を開発・販売せざるを得なくなった。
「三ない運動」への道
さらに、この社会的な反発は、教育現場にも波及した。1982年、全国高等学校PTA連合会は、「免許を取らせない」「買わせない」「運転させない」をスローガンとする「三ない運動」の推進を決議した。CB750の登場がこの運動の直接的な原因ではない。しかし、CB750が火を付けたナナハンブームと、それが助長した70年代から80年代にかけての暴走族文化が、社会にバイクに対する強い警戒心を生み、最終的にこの運動へと繋がったことは間違いない。三ない運動は、CB750が生み出した「速さ」と「反抗」の文化に対する、社会の遅れてきた免疫反応といえよう。
二つの遺産
かくしてCB750は、日本において二重の遺産を持つマシンとなった。一方では、日本の技術力の結晶であり、世界に冠たる工業製品の象徴として賞賛される。そしてもう一方では、社会秩序を揺るがし、反逆のアイコンとなり、結果として日本のモーターサイクル市場を長年にわたり縛り付けることになる厳しい規制を生み出すきっかけとなった、破壊的な存在としても記憶されている。このマシンの技術的な成功は、あまりに偉大であったがゆえに、その力が社会に与える影響をコントロールできなくなった。CB750は、自国において英雄であると同時に、アンチヒーローでもあるという、他に類を見ない宿命を背負ったモーターサイクルなのである。
The Dream Machine: How the Honda CB750 FOUR K0 Defined an Era
In 1969, at the zenith of Japan's high-speed economic growth--an era often called the "Shōwa Genroku"--a single motorcycle fundamentally overturned the history of motorcycling worldwide. That machine was the Honda Dream CB750 FOUR. Born as a symbol to showcase Japan's technological prowess and confidence after its postwar reconstruction, it was more than a mere industrial product; it was the very embodiment of the spirit of the age.
Its legend began even before its release, at the 1968 Tokyo Motor Show. The prototype, unveiled with specifications that far exceeded the conventions of the time--including the world's first mass-produced inline-four SOHC engine and hydraulic front disc brake--sent shockwaves through riders and experts globally. Its smooth, powerful engine, reminiscent of a GP racer, and its revolutionary brakes capable of safely stopping from a top speed of 200 km/h, truly presented the standard of the future. The CB750 earned the title "King of the Road Machine" before it even went on sale.
The arrival of the CB750 created a new market category, the "superbike," and sent a massive shockwave through global manufacturers. Its rival, Kawasaki, was notably forced to scrap its plans for a 750cc vehicle then in development and instead create the 903cc "Z1" to surpass the CB750 in every aspect. Thus, the fuse was lit for the fierce "'Nanahan' (750cc) Wars" of the 1970s.
What solidified its fame was its dramatic victory at the 1970 Daytona 200. Amidst a grueling race where factory machines retired one after another due to mechanical trouble, this victory, secured by the masterful control of veteran rider Dick Mann, proved the CB750's high performance on the world's most prestigious stage.
However, contrary to its brilliant achievements, it left a complex legacy in its home country of Japan. Its overwhelming performance and presence became a symbol for "bōsōzoku" youth gangs expressing rebellion against society, developing into a serious social problem. In response to this situation, under administrative guidance, manufacturers introduced a voluntary restriction on domestic sales, capping engine displacement at 750cc. Furthermore, it became a remote cause for the social trend that led to the "'Three No's' Movement," which, in principle, prohibited high school students from using motorcycles.
A hero that conquered the world as a pinnacle of technology, yet also an anti-hero that disrupted social order at home--the story of the CB750 FOUR's light and shadow eloquently tells how this machine was not just a motorcycle, but an extraordinary presence that defined an entire era.
夢幻機車:本田 CB750 FOUR K0 如何定義一個時代
1969年,正值日本被譽為「昭和元祿」的高度經濟成長巔峰時期,一輛摩托車從根本上顛覆了世界摩托車的歷史。它就是本田 Dream CB750 FOUR。這台機車的誕生,是為了向世界展示日本在戰後重建中所達成的技術實力與自信的象徵,它超越了單純的工業產品,體現了那個時代的精神本身。
它的傳奇始於上市前的1968年東京車展。當時發表的原型車,搭載了世界首款量產的並列四缸SOHC引擎和油壓式前碟煞,其規格遠超當時的常識,震撼了全球的騎士與專家。那具讓人聯想到GP賽車的光滑而強大的引擎,以及能從200km/h的最高時速下安全煞停的劃時代煞車系統,無疑提示了未來的標準,使CB750在發售前就獲得了「公路之王」的稱號。
CB750的登場創造了「超級摩托車」這一全新市場,並對全球製造商帶來了巨大的衝擊。特別是其競爭對手川崎,被迫放棄了當時正在開發的750cc車款計畫,轉而催生出在各方面都超越CB750的903cc「Z1」。就這樣,70年代激烈的「『Nanahan』(750cc級距)戰爭」揭開了序幕。
使其聲名不朽的,是1970年在 Daytona 200 英里大賽中的戲劇性勝利。在這場廠隊賽車因機械故障接連退賽的嚴酷競賽中,憑藉資深車手迪克・曼(Dick Mann)的精湛操控所奪下的勝利,在世界最高殿堂證明了CB750的卓越性能。
然而,與其輝煌功績形成對比的是,它在日本國內留下了複雜的遺產。其壓倒性的性能與存在感,使其成為了反抗社會的年輕群體「暴走族」的象徵,並發展成嚴重的社會問題 。為應對此一情勢,在行政指導下,製造商們導入了將日本國內銷售車款的排氣量上限設為750cc的自主規範 。此外,這也成為了催生原則上禁止高中生使用摩托車的「三不運動」社會風氣的遠因之一 。
CB750 FOUR既是席捲全球的技術結晶英雄,同時也是動搖國內社會秩序的黑暗英雄。其光明與陰影的故事,雄辯地說明了這台機車不僅僅是一輛摩托車,而是一個定義了整個時代的非凡存在。
| Cubic capacity | 736cc | Maximum horse power | 67ps / 8,000rpm |
|---|---|---|---|
| Maximum torque | 6.1kg-m / 7,000rpm | 始動 | セル/キック始動 |
| 変速機 | 前進5速 | 乾燥重量 | 218kg |
| 最高速度 | 200km/h以上 | SS1/4マイル | 12.4sec |