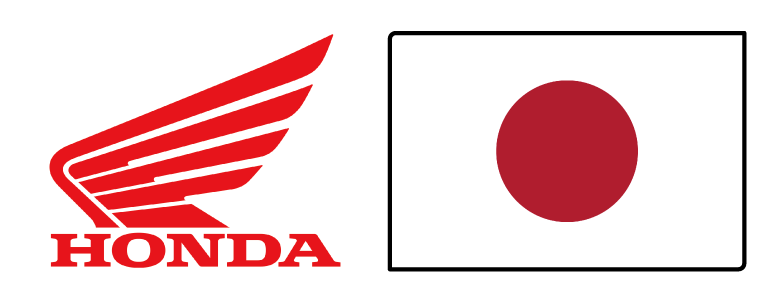 MOTOCOMPO
MOTOCOMPO
ポケットの中の革命:ホンダ・モトコンポ
モトコンポを生んだ世界:1980年代初頭の日本
危機を乗り越え、未来へ向かう経済
1980年代初頭の日本経済は、一つの大きな転換期にあった。1978年から79年にかけて世界を襲った第二次石油危機に対し、日本は驚くべき速さで適応し、欧米主要国が深刻な雇用問題に苦しむ中、それを回避することに成功した。実質GNP成長率は70年代に比べて鈍化したものの、国内経済の安定は国民に将来への確かな自信を与えた。
この時代の経済を牽引したのは、自動車や電気機器を中心とした輸出産業の目覚ましい隆盛だった。高品質で革新的な「メイド・イン・ジャパン」製品は世界市場を席巻し、日本は巨額の経常収支黒字を記録する。この輸出主導の成長は、アメリカとの間に深刻な貿易摩擦を引き起こす一因ともなったが、同時に国内のメーカーには、絶え間ない技術革新と独創的な製品開発への強い動機付けを与えた。
このような経済環境は、野心的で技術的に高度な消費者向け製品が生まれるための肥沃な土壌を形成した。世界的な輸出企業としてこのダイナミズムの中心にいた本田技研工業(以下、ホンダ)は、モトコンポのような前例のないアイデアを追求するために必要な資本力と、何よりも揺るぎない自信を兼ね備えていた。
新しい消費者:個性、ライフスタイル、アイデンティティの追求
経済的な豊かさは、特に若者文化に大きな変化をもたらした。戦後の集団的な復興から個人の表現へと価値観がシフトし、自分だけの「ライフスタイル」を構築することが新たな目標となった。
この時代、ファッションは自己表現の最も重要な手段だった。1980年代には、多種多様なスタイルが生まれ、街を彩った。横浜元町の上品なカジュアルスタイルに由来する「ハマトラ」や、アメリカの名門私立校の制服をルーツとする「ジャパニーズ・プレッピー」が女子大生や男子大学生の間で流行。その一方で、山本耀司や川久保玲といったデザイナーが手掛けるDCブランドの、全身を黒で統一した前衛的な「カラス族」も登場し、大きな衝撃を与えた。年代後半には、渋谷に集まる高校生を中心に「渋カジ(渋谷カジュアル)」という新たな潮流も生まれた。
重要なのは、これらが単なる服装の流行に留まらなかった点だ。『JJ』のようなファッション雑誌がライフスタイルの指南書として絶大な影響力を持ち、『オフィシャル・プレッピー・ハンドブック』といった書籍がベストセラーになるなど、ファッションは日常生活や価値観と不可分に結びついていた。また、松田聖子やチェッカーズといったアイドルが若者のファッションや行動に大きな影響を与え、彼らのスタイルを模倣することが一大ブームとなった。
さらに、大量生産品から距離を置き、自己の個性をより強く表現する手段として、アメリカから輸入された古着に価値を見出す「ヴィンテージブーム」も起こった。これらすべての現象は、消費者が単にモノの機能性を求めるのではなく、そのモノが持つ物語やイメージを通じて自己のアイデンティティを表現しようとしていたことを示している。
モトコンポとそのパートナーであるシティは、この新しい消費者の価値観に完璧に応える製品だった。シティの遊び心あふれるファッショナブルなデザインと、モトコンポの奇抜で持ち運び可能な性質は、個性、自由、そして未来志向の都会的な感性の象徴だったのだ。
モトコンポという名称自体が、この時代の精神を雄弁に物語っている。「モト」はモーターバイクから、「コンポ」は当時流行していたコンポーネントステレオから取られた。この名前は、単なる乗り物ではなく、パーソナルな技術製品としてこの製品を売り出すという明確な意図を反映している。1979年に発売されたソニーのウォークマンは、音楽を個人のもの、そしてポータブルなものへと変え、世界中のライフスタイルに革命をもたらした。モトコンポの「持ち運べるバイク」というコンセプトは、このウォークマンが切り開いた「パーソナル・ポータブル技術」の思想を、移動手段の領域に応用しようとする試みだった。それは、いわば「移動のためのウォークマン」を創造しようとする野心的な挑戦であり、80年代の技術と文化の潮流が交差する点に生まれた、時代を象徴する製品だった。
共生する創造:シティとモトコンポ、前代未聞の二輪・四輪同時開発
ホンダ・シティとモトコンポは、単体で評価されるべき二つの製品ではない。それらは、統合されたモビリティシステムとして構想された、一つの創造物としてみるべきだ。この「世界初」と謳われた開発アプローチは、ホンダ独自の企業文化と、時代が求める新しい価値観の融合から生まれた。
ホンダの精神:「良いものをつくれば、必ず売れる」
1980年代のホンダは、業界の常識に挑戦し続ける、技術者主導の異端児として知られていた。創業者・本田宗一郎から受け継がれたこの文化は、保守的な市場論理よりも、革新的なアイデアと卓越した技術を優先するものだった。同社は、既存の市場に応えるのではなく、新たな市場を創造する「提案型の商品」で評価を得ていた。
四輪車と二輪車を同時に、しかも一つのコンセプトの下で開発するという試みは、自動車史上前例のないものだった。これは、他のメーカーが決して踏み込まない領域に挑戦するホンダの意欲と、リスクを恐れない企業精神を示している。
「トールボーイ」革命:ホンダ・シティのデザイン
ホンダ・シティは、当時の自動車デザインの主流であった「低く、長く」というトレンドに対する明確な挑戦状だった。その核心にあったのが、「トールボーイ」という画期的なデザインコンセプトだ。
全長3,380mm、全幅1,570mmというコンパクトなボディに対し、1,470mmという異例の高さを与えることで、クラスの常識を覆す広々とした室内空間を実現した。これは、現代のトールワゴンやミニバンの先駆けとも言える発想だった。このコンセプトを具現化するため、開発チームにはターゲット層と同じ20代の若いスタッフが起用され、彼らの感性が存分に反映された。
デザインは、直線基調で無駄な装飾を排した、クリーンで合理的なものだった。これは見た目のスタイリッシュさだけでなく、室内空間を最大限に確保するという機能的な目的にも貢献しており、その徹底した機能美はドイツ車にも通じる雰囲気を持っている。そのシティのデザインは、モトコンポという存在が生まれるための「機会」の創出を促した。その背が高く、箱型のトランクこそ、モトコンポが収まるべく特別に設計された「ガレージ」だった。
「トランクバイク」という発想:アクセサリーとしての機動性
モトコンポは、開発当初からシティでの体験を構成する不可欠な要素として考えられていた。その目的は、キャンプ場や公園、サーキットといった目的地にクルマで到着した後、最後の「ラストワンマイル」を自由に移動するための手段を提供することだった。
シティのトランクルームには、モトコンポを安全に固定するための専用アンカーナットが標準装備され、オプションで専用のタイダウンベルトも販売されていた。これは、二つの製品が設計の初期段階から一つのシステムとして計画されていた動かぬ証拠である。
この「クルマ+バイク」というシステムは、長距離移動の利便性と、現地での散策の楽しさや柔軟性を両立させる、新しい形のレジャーの自由を提案した。それは、ホンダのDNAに刻まれた「遊び心」が具現化したものであり、移動を単なるA地点からB地点への行為ではなく、生活を豊かにする体験へと昇華させようとする試みだった。
この開発プロセスは、モビリティに対する「システム思考」アプローチの優れた実践例である。一方の乗り物の設計上の制約が、もう一方の設計を直接的に規定し、共生的な関係を築いている。シティの「トールボーイ」デザインが、そのクラスでは異例の広さとアクセスしやすい荷室空間を生み出し、モトコンポはその特定の空間に完璧に収まるという制約の下で設計された。つまり、ホンダが市場に投入した真の「製品」とは、一台のクルマやバイクではなく、移動とレジャーのための統合された「システム」そのものだった。
さらに、四輪と二輪を同時に開発するという前例のないプロセス自体が、強力なマーケティングツールとして機能した。実際、大きな話題を呼び、ホンダの革新的な企業イメージを社会に強く印象づけた。
「箱」のエンジニアリング:モトコンポのデザインと技術的独創性
大統領令と時間との戦い
モトコンポの開発は、長期的に計画されたプロジェクトではなかった。それは、シティの市販化が目前に迫る中で、トップダウンの特命によって始まった。
開発は、当時のホンダ社長による「シティに積めるバイクを造れ」という、シンプルかつ絶対的な「社長勅命」によってスタートした。この命令が下されたのは、シティの発売までわずか半年という差し迫った時期であり、開発は「突貫工事」のようなスケジュールで進められた。驚くべきことに、この困難なタスクを担った開発チームはわずか4名、設計の実務は2名という極めて小規模な体制だった。
しかし、この異例の状況には一つの利点があった。社長の命令はコンセプトの実現に主眼を置いており、コストに関する言及がなかったため、チームは予算の制約をあまり気にすることなく、デザインと技術的な解決策を最優先することができた。この特異な開発環境が、最終的に8万円という当時の原付としては比較的高価な価格設定につながった一方で、妥協のない独創的な製品を生み出すことを可能にした。
機能が形を創る:「箱」というデザインの必然性
モトコンポのアイコンである長方形のフォルムは、ただの奇抜なスタイリングではない。それは、「完璧に収納可能であること」という第一の設計要件から導き出された、当然の帰結だった。
開発チームの核となるデザインコンセプトは「箱」。これを実現するため、彼らは折りたたんだ際に「上面を平らに出来るようにする事」に徹底的にこだわった。この制約が、車体全体のレイアウトを決定づけた。49ccの2サイクルエンジン(AB12E型)、燃料タンク、オイルタンク、バッテリーといった主要コンポーネントはすべて、メインフレームの水平ラインよりも下に配置された。
この低重心なパワートレイン配置によって生まれた上部の空間に、ハンドル、シート、ステップが完全格納されるように設計された。各パーツは巧みな機構によってボディ内部に折りたたまれ、最後に専用のカバーを閉じることで、完全にフラットな長方形の美しいフォルムが完成する。
携帯性のための革新:安全な輸送を実現する技術
バイクを折りたたむだけでは、コンセプトは未完成だった。クルマの室内に積載し、横倒しにして輸送しても、燃料やオイル、バッテリー液が漏れないという安全性を確保する必要があった。
ホンダの技術者たちは、この課題を解決するために、完全密閉型の燃料タンクや逆止弁を含む、特殊な液漏れ防止機構を開発した。これにより、モトコンポは横置きでの輸送が可能となり、トランクバイクとしての実用性が飛躍的に向上した。
さらに、車体にはシティのトランクにしっかりと固定するためのタイダウンベルト用フックが4箇所に設けられていた。高度な技術が詰め込まれているにもかかわらず、車体は驚くほど軽量で、乾燥重量はわずか42kg(車両重量45kg)に抑えられており、大人2人であれば容易に持ち上げて積載することができた。
モトコンポは、制約下におけるデザインの傑作と言えよう。時間、サイズ、形状、安全性といった極端な制約は、創造性を阻害するどころか、むしろ技術的な規律と独創性を極限まで引き出し、その象徴的なデザインへと結実させた。主要な制約である「シティのトランクに収まること」が、「長方形で平らな上面を持つ」という二次的な制約を生み、それがさらに「エンジンはどこに置くか」「ハンドルはどう折りたたむか」「液体漏れをどう防ぐか」といった三次的な技術課題を派生させた。最終的なデザインは、これらの課題解決のプロセスを反映したものであり、一切の無駄がない。
また、モトコンポのデザインは、「遊び心」と「ブルータリズム(荒々しさ)」という一見矛盾した二つの要素を内包している。そのパブリックイメージはキュートで、おもちゃのような親しみやすさを持ってはいるが、その根底にあるデザイン言語は、機能性をむき出しにした、ほとんどブルータリスト的とも言える幾何学的なものだ。一般的なスクーターに見られる曲線的なフォルムを排し、収納性という機能を最優先した結果生まれた硬質で妥協のない形状。その「可愛らしさ」は、小さなスケールと鮮やかなカラーリングから後天的に生じるものであり、厳格な機能主義との間に生まれる緊張感が、モトコンポを単なる「可愛いスクーター」以上の、複雑で魅力的なデザインオブジェクトへと昇華させている。
| 項目 | スペック |
|---|---|
| 型式 | NCZ50 |
| エンジン種類 | AB12E型 空冷2サイクル単気筒 |
| 総排気量 | 49cc |
| 最高出力 | 2.5PS/5,000rpm |
| 最大トルク | 0.38kgf-m/4,500rpm |
| サイズ(展開時 L×W×H) | 1,185mm×535mm×910mm |
| 乾燥重量 | 42kg |
| 車両重量 | 45kg |
| 燃料タンク容量 | 2.2L |
| オイルタンク容量 | 1.0L |
| 燃費 | 70.0km/L(30km/h定地走行テスト値) |
| タイヤサイズ(前/後) | 2.50−8 |
| 当時価格(1981年) | 80,000円 |
ブームとなるマーケティング:マッドネスのCMと「シティは、ニュースにあふれてる。」
この型破りな製品を市場に送り出すため、ホンダは同様に型破りな広告キャンペーンを展開した。その成功の鍵は、製品のスペックを語るのではなく、ライフスタイルと時代の高揚感を売り込むことにあった。
ジングルの力:マッドネスと「ムカデダンス」
ホンダは、シティとモトコンポのローンチキャンペーンに、当時イギリスで絶大な人気を誇っていたスカバンド「マッドネス」を起用した。これは、日本の自動車広告としては極めて異例の選択だった。
テレビコマーシャルでは、メンバー全員が奇妙でコミカルな「ムカデダンス」を披露。BGMには、日本の著名な作曲家である故・井上大輔氏がこのCMのために書き下ろした、非常にキャッチーな楽曲「In the City」が使用された。その歌詞は、「ホンダ、ホンダ、ホンダ、ホンダ」と「シティ・イン・シティ」というフレーズをひたすら繰り返すという、極めてシンプルなものだった。
このキャンペーンは社会現象とも言える大成功を収めた。楽曲とダンスは子供たちの間でも大流行し、学校の運動会で使われるほどだった。その影響はあまりに大きく、多くの日本人にとってマッドネスは本来の音楽性よりも「ホンダ・シティのバンド」として記憶され、「コミック・バンド」というイメージが定着したほどだ。このCMは、それ自体が80年代を象徴するポップカルチャーの一部となったのだ。
物語の構築:「シティは、ニュースにあふれてる。」
キャッチフレーズの「シティは、ニュースにあふれてる。」
この言葉は、図らずとも製品が持つ革新的な性質を見事に要約していた。
このフレーズは、クルマの名前である「シティ(街)」と、このクルマの登場自体が「ニュース」であるという二重の意味を持つ、巧みな言葉遊びだった。そして、その言葉は決して誇張ではなかった。トールボーイという新しいデザイン、世界初の四輪・二輪同時開発、トランクに収まるバイク「モトコンポ」の存在、そしてマッドネスを起用した高エネルギーなCM。そのすべてが、まさに「ニュース」だった。
このキャンペーンは、シティを単なるエントリークラスの小型車ではなく、楽しさに満ち、階級を感じさせない、市場における刺激的な新しい提案として位置づけることに成功した。
このマーケティング戦略は、当時の日本の若者が抱いていた海外ポップカルチャーへの憧れを巧みに利用した、洗練されたものだった。イギリスの人気バンドを起用することで、ホンダは「クール・ブリタニア」の断片を意図的に輸入し、製品に投影した。国内のスターではなく海外のアーティストを選ぶことで、シティには即座にコスモポリタンで非伝統的なイメージが付与された。
さらに重要なのは、このキャンペーンが「機能」ではなく「感情」を売った点だ。CMは、エンジン性能や燃費、荷室の広さといった技術的なスペックにはほとんど触れなかった。その代わりに、 joyous(喜びに満ちた)、chaotic(混沌とした)、urban energy(都会的なエネルギー)といった感覚を伝えることに全力を注いだ。ターゲットであったライフスタイル志向の若者にとって、スペックの羅列よりも「シティ/モトコンポ=楽しい」という強力な感情的結びつきを形成することのほうが、はるかに効果的だった。これは、80年代の新しい消費者にとって、製品の「何(what)」よりも「なぜ(why)」、つまりそれがもたらす感情や体験の方が重要であるという、マーケティング哲学の変化を象徴する出来事だった。
第二の人生:『逮捕しちゃうぞ』によるモトコンポの神格化
モトコンポは1985年に生産を終了し、5万台以上が販売された。これは決して失敗とは言えない数字ですが、爆発的なヒットというほどではなかった。しかし、その生産終了後にこそ、モトコンポの真の物語は始まる。漫画・アニメ作品『逮捕しちゃうぞ』への登場が、この小さなバイクを単なる過去の製品から、不朽のカルト的アイコンへと昇華させたのだ。
乗り物からキャラクターへ:『逮捕しちゃうぞ』におけるモトコンポ
モトコンポの生産が終了した翌年の1986年、漫画家・藤島康介氏による『逮捕しちゃうぞ』が連載を開始した。女性警察官コンビの活躍を描くこのアクションコメディ作品は、モトコンポに第二の、そしてより永続的な生命を吹き込むことになる。
作品の中で、モトコンポは主人公たちが乗るミニパトカー「ホンダ・トゥデイ」のトランクに搭載される特殊装備として、重要な役割を担う。この作品は、バイクやクルマといったメカニックの描写が非常にリアルで緻密であることで高く評価されており、その中で描かれるモトコンポには、単なる道具以上の存在感とキャラクター性が与えられていた。狭い路地での追跡劇や、意表を突く作戦行動など、モトコンポはその小さな車体を活かして大活躍し、ヒロインたちの頼れる相棒として描かれた。
「逮捕仕様」という新たなアイデンティティ
この作品は、モトコンポに全く新しい、象徴的なイメージを与えた。劇中に登場するモトコンポは、パトカーと同様の白と黒のツートンカラーに塗装され、小さな赤色灯が取り付けられていた。このスタイルはファンの間で「逮捕仕様」として知られるようになり、モトコンポの新たな代名詞となった。
1998年までに累計600万部を売り上げる大ヒットとなった原作漫画と、それに続くアニメシリーズの成功は、生産終了から何年も経って忘れ去られかけていたモトコンポを、全く新しい世代の観客に紹介した。その人気は中古車市場にも直接的な影響を及ぼし、作品の影響でモトコンポを求めるファンが急増。価格は高騰し、コレクターズアイテムとしての地位を確立した。
この文化的な影響力は絶大で、現在でもプラモデルやカプセルトイなどの商品では、オリジナルのカラーリングと並んで、この「逮捕仕様」がラインナップされることが多く、その人気の根強さを示している。
『逮捕しちゃうぞ』は、モトコンポを自動車史の片隅に埋もれる運命から救い出す「文化的救出作戦」の役割を果たしたと言えよう。ホンダが当初提示した「レジャー」という抽象的なコンセプトに対し、この作品は「頼りになる警察の相棒」という具体的で魅力的な「物語」を与えた。物語はコンセプトよりもはるかに文化的な定着力が高く、結果として『逮捕しちゃうぞ』はモトコンポを文化的な意識の中に「再ローンチ」させ、その商業的な寿命をはるかに超える、永続的なアイデンティティを授けた。
藤島康介氏の慧眼は、モトコンポが元来秘めていた「キャラクターとしての潜在能力」を見抜いた点にある。その小さなサイズ、箱型のフォルム、そして2.5PSという非力な性能は、どこか健気で応援したくなるような「アンダードッグ(かませ犬)」の魅力を放っていた。作品の中で、モトコンポはその小ささという弱点を、狭い場所での機動性という強みに変えて活躍する。これは古典的なアンダードッグの物語構造そのものだ。作者は、この乗り物が持つ擬人化しやすい性質を的確に捉え、有能な女性主人公たちの手に委ねることで、マシンとキャラクターの完璧なペアリングを創り出した。これは、製品の文化的な成功が、その創造者でさえ完全には活用しきれなかった「本質的な個性」を、第三者であるアーティストが見出し、表現することによって決定づけられることがある、という興味深い事例となった。
ポケットサイズのアイコンが持ち続ける現代的意義
未来はコンパクトに:モトコンポの現代的遺産
モトコンポが掲げた核心的なアイデア、すなわち「他の交通手段と連携する、持ち運び可能なパーソナル・ラストワンマイル・モビリティ」は、1981年当時よりもむしろ現代において、より強い現実味と重要性を持っている。都市部の交通渋滞、環境問題、そして多様化するライフスタイルといった現代的な課題に対し、モトコンポのコンセプトは驚くほど的確な一つの答えを提示している。
それを証明する一つに、2023年に北米で発表された電動モビリティ「ホンダ・モトコンパクト」の存在がある。この新しいモデルは、初代の哲学を受け継ぎながら、電動化という現代的な技術で再構築されている。さらに小さく、スーツケースのような形状に折りたためるその姿は、1981年のビジョンが21世紀の課題に対応するために進化した形だ。
モトコンポの物語は、大胆で遊び心にあふれ、そして卓越した技術に裏打ちされた一つのアイデアが、いかにして自らの時代を超越し、未来のモビリティを創造するためのインスピレーションの源泉となり続けるかを示す証なのである。
Revolution in Your Pocket: The Honda Motocompo
In the early 1980s, after overcoming the Second Oil Crisis, Japan's economy stabilized. A culture that valued lifestyle and individuality bloomed, particularly among young people. Influenced by fashion magazines and pop idols, consumers began expressing themselves not just through function but through the stories and images of the products they owned.
The "symbiosis" of the Honda City and Motocompo perfectly symbolized this era. Honda, known for creating "proposal-based products" that went beyond existing markets, developed the City with its innovative "Tall Boy" design. Simultaneously, they created the Motocompo, a "trunk bike" that fit perfectly into the City's trunk. This unprecedented simultaneous development of a two- and four-wheeler was a tangible expression of Honda's corporate culture and playful spirit.
The Motocompo's design wasn't just a gimmick. It was born from a top-down mandate to "build a bike that fits in the City." A small team of four developed it in just six months. Its rectangular, "box-like" form was a necessary consequence of the design constraint to be perfectly stowable. It featured clever engineering, like handlebars and a seat that folded inside, and a liquid-leak-proof mechanism for horizontal transport.
The launch slogan, "The City is full of news," was spot-on. The commercial, featuring the British band Madness, became a social phenomenon, creating a powerful emotional link between the product and a sense of fun and urban energy. However, sales weren't a smash hit, and production ended in 1985.
After production ended, the Motocompo found a "second life" in an unexpected place: the manga and anime series You're Under Arrest! It appeared as a trusty sidekick for the heroines, an iconic "arrest-spec" vehicle that perfectly fit in their mini-patrol car. This series gave the forgotten Motocompo a new story and character, reigniting its popularity. Prices soared, and it became a sought-after collector's item.
The Motocompo's story is a fascinating example of how a product's cultural success can be shaped by a third-party artist. Its core concept of "portable, personal mobility that links with other transportation" is even more relevant today amid urban congestion and environmental concerns. The electric "Honda Motocompacto" released in 2023 is a modern legacy of the original Motocompo's forward-thinking vision.
口袋裡的革命:本田 Motocompo
在 1980 年代初期,日本經濟在度過第二次石油危機後進入穩定時期。一個特別注重生活方式和個人風格的文化,在年輕人之間蓬勃發展。受到時尚雜誌和流行偶像的影響,消費者開始不僅僅追求產品的功能性,而是透過產品所蘊含的故事和形象來表達自我。
本田 City 和 Motocompo 的「共生」完美地象徵了這個時代的精神。本田以創造超越現有市場的「提案型商品」而聞名。在其企業精神下,他們開發了擁有創新「高個子」(Tall Boy)設計的 City,同時也創造了 Motocompo 這款可以完美收納於 City 後備箱的「後備箱機車」。這種前所未有的二輪與四輪同時開發模式,是本田企業文化和玩樂精神的具體體現。
Motocompo 的設計並非僅僅是奇特的噱頭。它源於當時社長「造一台可以放進 City 裡頭的機車」的特令。一支僅四人的小團隊在短短六個月內完成了開發。其長方形、如「箱子」般的造型,是為了實現完美收納這一設計限制而誕生的必然結果。它具備巧妙的工程設計,例如可以收納於車體內的把手和座椅,以及防止液體外洩的特殊機制,使其能夠橫向擺放運輸。
上市時的宣傳口號「City,新聞不斷」(The City is full of news)恰如其分。由英國樂團 Madness 演出的廣告成了社會現象,在產品和樂趣、城市活力之間建立起強烈的情感連結。然而,銷售量並未達到轟動,產品於 1985 年停產。
停產後,Motocompo 在一個意想不到的地方找到了「第二春」:動漫作品《逮捕令》。它作為女主角們可靠的夥伴,以標誌性的「逮捕規格」車輛登場,完美地收納於她們的小型警車中。這部作品為這款幾乎被遺忘的 Motocompo 賦予了新的故事和角色性格,使其人氣重新燃起。價格隨之飆升,確立了其作為收藏品的地位。
Motocompo 的故事是一個引人入勝的案例,它證明了產品的文化成功有時不僅來自創作者,也可能來自第三方藝術家。其核心概念----「可攜式個人交通工具,能與其他交通方式相結合」----在今天這個充滿城市擁堵和環境問題的時代,顯得更加重要。2023 年發布的電動「本田 Motocompacto」,正是初代 Motocompo 超前思維的現代傳承。
| 全長 × 全幅 × 全高 | 1185 mm × 535 mm × 910 mm | 車両重量 | 42 kg |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 2.5PS/5000rpm | 最大トルク | 0.38kg-m/4500rpm |
| エンジン | 空冷2サイクル単気筒 | 総排気量 | 49 cc |
| フレーム形式 | バックボーン | 駆動方式 | チェーン駆動 |
| サスペンション(前) | テレスコピック | サスペンション(後) | ユニットスイング |
| 本体価格 | 80,000円(税込) | 生産台数 | 53,369台 |