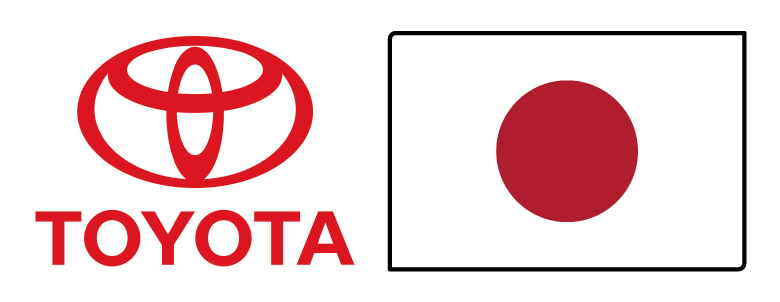 トヨモーター E8
トヨモーター E8
トヨモーター E8型
創業とトヨタとの関係
トヨモータース(Toyomotors)は、戦前にオートバイレーサーとして活躍し、戦後にトヨタ自動車の研究所に勤めていた川真田和汪(かわまた・かずお)氏によって、1949年に愛知県刈谷市で創立された。
社名の「トヨモーター」はトヨタにあやかったものであるが資本関係はなく、日新通商(現・豊田通商)との提携によりトヨタ自販の販売網を通じて製品を全国展開していた。
この販売体制から実質的にトヨタグループの一員ともみなされ、当時トヨタ系列ディーラーにとってもトヨモーターの販売好調は歓迎されていたと言われる。地元の愛知トヨタでは社内に「トヨモーター部」を設置するほど注文が殺到したとの記録もある。
製品の特徴と全盛期
創業当初、トヨモータースは自転車に取り付ける補助エンジン(いわゆるバイクモーター)を単体で製造・販売していたが、やがて型式認定を取得した完成車(オートバイ)の製造販売も手掛けるようになった。
自社工場ではエンジン以外の部品を外部メーカーから購入して組み立てるアッセンブリー方式を採用し、低コストで製品供給力を高めている。
戦後復興期には同社のバイクモーターやオートバイは手軽な庶民の足として飛ぶように売れ、需要拡大に伴い1953年には名古屋に工場を新設するなど生産体制を強化して月産6000台規模(エンジン単体と完成車の合計)を達成した。
トヨモーターの製品自体に際立った独創性はなかったものの、堅実な造りによる優れた耐久性ゆえに実用車として高く評価され、販売実績を伸ばしていった。こうした実用性重視の堅牢なバイクは、農村部や商業用途などで重宝され、多くのユーザーに支持された。
競合との競争と事業の終焉
昭和30年代(1950年代中盤)に入ると、国内のオートバイ市場は実用一辺倒の製品からスタイルや高性能を備えたモデルへと人気が移り始めた。
トヨモーターシリーズは引き続き耐久性と実用性を強調していたため新鮮味を欠き、ホンダ、ヤマハ、スズキなど後発メーカーが次々と魅力的な新型車を投入すると市場シェアを奪われていった。
さらに外注部品に頼る生産体制も高性能化への対応に限界を露呈し、品質面のトラブルが重なって経営は次第に傾いていく。事業立て直しの努力も実らず、1958年頃までに生産活動は停滞し、トヨモータースは1959年をもって事業を終了して約10年の歴史に幕を下ろした。
*同年にはホンダから名車スーパーカブC100が登場しており、市場の主役は小型軽量で扱いやすい新時代のオートバイへと移っていた。
E8型エンジンと四国自動車博物館の展示車両
トヨモーターE8型は、1950年代に同社の主力製品となった自転車用補助エンジン(原動機付自転車用エンジン)である。
排気量は88ccで、エンジン本体と取付金具をセットにして販売された。1953年から1958年ごろまで製造が続いたロングセラーで、「10万人の愛乗者を誇る」と当時の広告でうたわれるほど普及した。
堅牢なE8型エンジンを搭載した自転車バイクは耐久性が高く、当時は安価で手軽な移動手段として広く人気を集めた。
四国自動車博物館で展示されている車両もE8型エンジンを搭載しており、発売当時に人々の日常の足として活躍したモデルである。
また、輸送用途向けに車体右側へ荷台付きの側車(サイドカー)を装着したバリエーションも存在した。展示車両は往時の日本における庶民の足の一例として、国産オートバイ産業黎明期の歴史を今に伝えている。
| 製造 | 株式会社トヨモータース 1955年 | エンジン | 空冷2サイクル 単気筒 88.3cc |
|---|---|---|---|
| ボア&ストローク | 50mm × 45mm | 圧縮比 | 8:1 |
| 最大出力 | 2.9HP / 5000r.p.m | 最大トルク | 0.3kg-m/4900rpm |